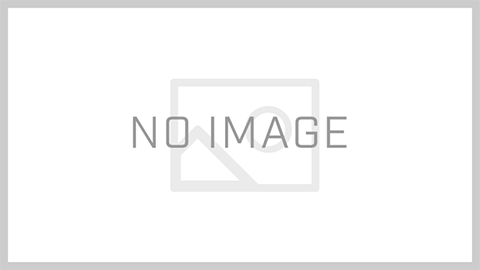- 社会不適合者とはどのような人?
- 社会不適合者に向いている仕事
- 社会不適合者の生き方
どうにもこの世の中で生きていくのが、苦しいと感じています。
20代中盤になっても、中二病をこじらせているのだろうか。絶賛モラトリアム中?
学生時代に感じていた、なんだかモヤモヤした気分をいまだ抱え続けているんです。
周囲を見渡せば、社会に上手く順応している人たちが多くなってきました。
社会人なりたての頃は、
- 明日会社に行くの面倒くさいな
- もう辞めたいな
そう言っていた友人たちも、上手く社会の波に乗っていくようになりました。
多少理不尽があってもそんなもんやろ?
働くってそういうことちゃうん?
といった、「当たり前」と言われる概念をすんなりと受け入れられる器の大きさ。
そして忍耐力。
僕はどうにも、その波に乗ることが出来ない。
これってもしかして社会不適合者なんじゃない?
会社員に向いてないんじゃない?
そんな風に考えたことは数えきれません。
- 毎日の出勤時間が決まっていること
- 無駄としか思えない会議や書類提出があること
- つきあい残業で帰れないこと
表面上では「はいはい」とすんなり受け入れている裏では、「なんでこんな訳のわからないルールがあるんだよ」と毒づいている自分がいるんです。
それに皆も「僕と似たようなコトを考えてるんじゃないの?」と思っていたけれど、どうにもそうではないらしい。
それでは僕みたいに、
- 上手く社会に適合できない
- 既存のルールに反発してしまう
人間はどのように生きていけばよいのでしょうか。
実体験を元に考えていきたいと思います。
そもそも「社会不適合者」って何だろう?
 そもそも「社会に適合できない人」とは、どのような人たちなのでしょうか。
そもそも「社会に適合できない人」とは、どのような人たちなのでしょうか。
疑問に思ったので、辞書で調べてみました。するとこんな解説が。
一言でいうと、
「社会の要求を受け入れられない人」
をいいます。
- 社会から提示されるルールに反発する
- 疑問があると行動できない
- 周囲の人間関係に馴染めない
といった特徴は、社会不適合者の代表的なものになります。
社会不適合者の3つの特徴
協調性がない
社会不適合者の特徴として挙げられるのが、「協調性がない」ことです。
例えばチームで仕事を進めていたときに、問題が発生したとします。
その際に、「自分には関係ないから」と無視をしたり、助けないといった行為は「協調性のなさ」に当てはまるでしょう。
周りと歩調を合わせることができないので、学校や職場では孤立してしまう可能性があります。
コミュニケーションが苦手
- 初めて出会う人と何を話せばいいかわからない
- 意志の伝達が上手くいかない
- 相手の目を見て話せない
- 沈黙が続く
といった特徴がある人も、社会不適合者な印象を与えてしまうかもしれません。
自身の経験だと、高校時代はまったくクラスに馴染むことができず、友人を作ることができませんでした。
また女性が怖くて目を見て話せなかったり、初対面では沈黙が続いて気まずい雰囲気になったりと、失敗の連続で苦しい思いをしました。
ただし、上記の項目は裏返すと
- 相手のことを考えて、話す内容を熟慮している
- 相手を傷つけないように、慎重に言葉を選んでいる
ことを意味します。
もしかすると、コミュニケーションが苦手な方は、プラス面を考えてみると良いのかもしれません。
「常識を素直に受け入れること」ができない
人に限らず、生き物は他者との生活の中で「社会」を形成します。
その過程においては様々なルールが生まれます。
例えば、
- 人を殺してはいけない
- ものを盗んではいけない
- 脱税してはならない
といったルールが社会にはありますが、元々はそんなものありませんでした。
誰かが「ものを盗んだ」という過去があったから、今後はそのようなことがないようにとルールが作られた。
そしてルールは積み重なり、いつの間にか社会の「常識」となったのです。
この「社会のルール=常識」となりますが、常識がいつの時代も通用するとは限りません。
人の価値観や環境は移ろいゆくものだからです。
その結果、
- 今の時代、リモートワークが出来ないなんて遅れているんじゃない?
- 会社にスーツとネクタイは必要ないでしょう?
といった、常識に疑問をもつ人間が出てきます。
彼らのことを一般に社会不適合者と呼ぶのでしょう。
社会不適合者は、どうやって世の中を生きていけばいいのか?
「会社で働く(サラリーマン)」という選択肢
社会に適合できないといったところで、食料を調達しなければ生きることができません。
「何も食べなくてOK」な身体になっていればいいけれど、生きている以上、そんなことはありえない。
それでは、どうやって食料を調達すればいいのでしょうか?
現代の社会だと、「会社に勤めて働く」ことが最もありふれた方法でしょう。
会社で働いてさえいれば、毎月決まった給料が貰えるので、餓死することはありません。
また
- 周りの人と会話ができる
- 協調しながら物事を進めるのが楽しい
- 会社でしかできない体験ができる
といった、オマケもついてくるでしょう。
お金だけではなく、それ以外のインセンティブもたくさんあるのです。
「サラリーマン以外」の選択肢
もちろん「働く」というのは、会社に勤めることだけが唯一の正解ではありません。
他にも、
- 自営業(フリーランス)
- 経営者
- 投資家
- 副業サラリーマン
といったサラリーマン以外の選択肢もあります。
どうしてもサラリーマンが合わない場合には、検討してみるといいでしょう。
国の調査によると、就業者の割合は
15~64歳の女性は70.6%,
25~44歳の女性は77.4%
15~64歳の男性は83.8%
というデータが出ています。
つまり、「日本の7割以上=サラリーマン」なのです。
その結果、僕たちは「働く=企業で雇われて働く」という図式で労働をイメージしてしまいがちです。
サラリーマン以外の選択肢があるという事実を知るだけで、気持ちが楽になります。
参照:内閣府 男女共同参画局
社会不適合者に向いてる環境・仕事
社会不適合者にとって大切なのは、
自分にとって、
- 適切な環境
- 適切な職業
とは何か?
を知ることなのだと思います。
たしかに、「社会不適合者にとって苦手な部分」があるのは事実です。
しかしどんな物事にもプラスとマイナスがあるように、「社会不適合者にとって得意な部分」もあるはず。
自分の特性や性格を知るコトで、
- ストレスが軽くなる
- 楽しんで仕事に取り組める
- 不安に感じる場面が減る
ことが期待できます。
向いている環境とは?
一人で黙々と作業ができる
コミュニケーションが苦手な場合、「人と頻繁に関わらない環境」で働くことを検討してみてはいかがでしょう。
ただし一人で黙々とは言っても、「すべてが一人だけで完結」する仕事は少ないです。
一部の作業は個人で出来たとしても、打ち合わせや報告といった最低限の関わりは発生するからです。
ただ営業や接客業のような緊密な連携は不要なため、快適に仕事が行えるはずです。
好きや得意を活かすことができる
興味のあることや得意なことを活かすことで、仕事の時間が楽しくなるかもしれません。
例えば
- テレビゲーム
- スポーツ
- 読書
- 映画鑑賞
- 料理
大好きなことをしている時間は、あっという間に過ぎてしまった。
そのような経験をした方も多いのではないでしょうか。
仕事を好きになると、仕事の時間は楽しく有意義なものになります。
好きになるためには、対象への興味・関心はもちろん、得意なことを活かせる環境であるかも重要です。
向いている仕事とは?
それでは社会不適合者に向いている仕事には、どのようなものがあるのでしょうか。
荷物の配達員
例えばトラック運転手の仕事には、
- 物資の運搬を行う
- 荷物の積み下ろしがある
- 勤務時間が不規則
といった業務があります。
荷物の荷卸しに多少のコミュニケーションは必要ですが、基本的には一人で行う仕事です。
一人時間が苦にならない人にはオススメです
また「トラック運転手=長距離運転」のイメージがあるかもしれませんが、
- 新聞配達
- 宅急便の配達
- コンビニへの荷物配達
といったように、配達する商品や距離は様々です。自分に適したものを選択するとよいでしょう。
工場作業員
工場の仕事には、
- フォークリフトでの荷物運搬
- 商品の仕分け、梱包
- 自動車の組み立て
といった業務があります。
基本的には人間ではなく、「物」と向き合う仕事であるため、接客業に比べるとコミュニケーションの機会は少ないです。
またルーティン作業も多く、頭脳労働が疲れるという方にもおすすめです。
ライター
ライターの仕事には、
- 広告のキャッチコピーを考える
- Web、雑誌、新聞、フリーペーパー等の媒体への投稿
などがあります。
最近ではWebメディアが主流となってきており、紙媒体での仕事からWebを中心とした仕事へシフトしつつあります。
ランサーズ(Lancers)のようなクラウドソーシングを利用することで、個人であっても企業から簡単に仕事を受注することができます。
基本的にはパソコンでの作業になりますので、マイペースに仕事を進めていくことができるでしょう。
クラウドソーシングで仕事を受注する際には、ライティングの資格があると文字単価を上げることができます。
先日クラウドソーシング実務士の資格を取得しましたので、体験談を載せておきます。
>>comming soon…
ランサーズの登録は無料ですので、とりあえず登録だけしておきましょう。
エンジニア
エンジニアといっても様々な種類があり、
- Webデザイナー
- Webサイト製作
- 組み込みエンジニア
- ネットワークエンジニア
- セキュリティエンジニア
と多岐に渡ります。
エンジニアは「客先常駐」としてキャリアをスタートさせる場合が多いです。
僕自身も以下の流れで、IT業界に潜り込みました。
- 大学卒業
- 法人営業職
- 組み込みエンジニア(客先常駐)
エンジニアになりたい方は、以下の記事も参考にしてみてください
>>comming soon…
本当にサラリーマンを辞めたいの?
働きたくないのか、それとも会社員でいられないのか

僕の場合、そもそも”働くこと”自体が嫌いなわけではありません。
誰かに喜んでもらうのは好きですし、誰かの希望を叶えてあげたいという気持ちは持っています。
けれども会社で働く場合、希望を通すためには、必ずしがらみやルールといった規定を乗り越える必要が出てくるのです。
ちょっとしたことでも稟議を通す必要があったり、顧客のためよりも自社の利益を最優先するといったように。
もちろん、そうしたルールを守るコトで上手く行くことも沢山あるのでしょう。
そもそも、ルールがないと組織は無茶苦茶になってしまいますし、統制が効かなくなってしまいます。
ただ、どうしても自分にはその環境が適していないのであれば、他の選択肢を検討することも必要になってくるでしょう。
社会不適合者は”自分の居場所”を作るしかない
社会は、大多数の意向が反映されて形成されています。
小学校入学と同時に「友達100人出来るかな♪」と歌わされるように、人と協調できる人間が正義といった世の中です。
適応できる人にはイージーだけど、そうじゃない人間にとっては非常に辛いですよね。
僕だって幾度となく、「社会で要請される理想像になれたらな〜」と考えました。
- 明るく
- 社交的で
- 快活でおしゃべり
- 人の気持ちが読めて
- どんな人とでも協調できる
そんな理想とは掛け離れている自分の姿を省みては、何度も落ち込みました。
けれども、社会で生きていくためにはどうにかして状況を変えなければならない。
僕にできることといえば、
- 自分のことを見つめなおす
- 何が得意で不得意かを理解する
- 自分の居場所をつくる
しかないのだと考えています。
社会人になってからというもの、僕自身は迷いながら生きてきたように思います。
これから先、何十年と続く未来をどうやって生きていけばいいのだろうか?
そんな問いを常に考えてきたし、今でもその気持ちは消えず、心の奥底でモヤモヤを抱き続けています。
今は「はいはい」と表面上では笑って受け流すことができ、順応しているように見せられているけれども、あと何十年もこの生活が続くと思うと、「絶望」の2文字しか思い浮かびません。
- どこかで必ず爆発する
- 現実から逃げだしてしまう
そうなる自分の姿が想像できるからこそ、できることは何でもやってみようと考えているのです。
すぐに会社を辞めるべきではない?
ネット上には、「嫌なら辞めちまえよ」とか「簡単に稼げる方法があるんだから」といった、甘〜い言葉が溢れています。
心が疲れて、何かに縋りたい人にとって、これほど嬉しい言葉はないはずです。
- 僕に共感してくれる人がいるんだ
- こんな環境から飛び出してやる
簡単に飛び出してしまう人もいることでしょう。
でも、
と疑問に感じます
もちろん、今いる環境が辛くて、病気になってしまいそうだとか、限界だという人はすぐに逃げた方がいいと思います。
抜け出すのも勇気がいりますが、身体を壊してしまうくらいなら、逃げ出した方がよっぽどましでしょう。
ただし、もし少しでも気持ちに余裕が持てるのであれば、今の環境を続けながら、自分にできることを他にも探してみてはどうでしょう。
まずは、
「どのような生き方をしたいのか」をじっくり考える。
その上で、「一人で出来る仕事がしたい」とか「個人で食い扶持を稼いでやる」とか、自分の本当の気持ちを見つめ直してみるんです。
そして、実際に行動に移してみることです。
副業から人生の選択肢を広げよう
例えば、文章を書くことで生計を立てたいという理想があるなら、ブログや出版社に投稿してみるとよいと思います。
続けていれば、本の出版やライターの仕事がもらえるかもしれませんし。
お金を稼げるのであれば、それを仕事にしてもいいですし、仕事にできないとしても
自分は違う仕事をしても食べていけるんだ
という安心感が得られます。
はたまた、やっぱり自分には「書く仕事は向いていなかったな….」と気づけるかもしれません。
自身の将来像を思い描いた上で、一つ一つできることをやってみるしかないのです。
成功しても失敗しても行動に対する結果が得られます。
今は失敗だと思ったことでも、本当は失敗ではないかもしれません。
なぜなら、その失敗は、成功するための一つのプロセスかもしれないからです。
僕の場合、初めに勤めた会社で体調を崩したことが将来を考えるきっかけとなりました。
その時の想いをまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。
>>アトピーが教えてくれたこと | 病気になって景色が変わった話
>>仕事のストレスで限界を感じたら | 心身を壊す前に心の声を聞こう
>>1円を笑う者は1円に泣く | 1円を稼ぐと雪だるま式にお金は増えていく
また将来のために、ライティングとプログラミングの資格を取得しました。
体験談を書いていますので、よろしければ読んでみてください
Webライティング資格を取得した際の体験談はこちら
>>comming soon…
C言語プログラミング認定試験を取得した際の体験談はこちら
>>C言語の資格「C言語プログラミング能力認定試験」| 試験の概要とおすすめ本・学習サイト
>>>【C言語の資格】C言語プログラミング能力検定試験2級合格【体験記】
最後に
社会に適応できない人間にとって、生きるのは苦しいものです。
誰からも理解されず、周囲に馴染むことができない。失敗ばかりで嫌なことが続くと、すべてを投げ出してしまいたくなることもあるでしょう。
ただ僕はそんなときであっても、諦めずに前を向いて生きていきたいと思っています。
別に何度失敗したっていい。
死にさえしなければやり直しは何度でもできると信じています。
社会不適合者が生きていくのに大切なのは、以下の3点だと考えます。
- 一度立ち止まって、自分の気持ちを見つめ直してみる
- 今いる環境に留まれる余裕があるならば、その状態で出来ることをやってみる
- 少しずつ選択肢の幅を増やし、生きていく術を獲得する
まずは自分のできるところから、一歩踏み出してみましょう。
ここでは実際に読んでみて、人生を考え直すきっかけになった本をご紹介したいと思います。ビ
ジネス本のような「~術」ではないためすぐに役には立たないかもしれませんが、物事の考え方・見方に影響を与えてくれると思います。
僕は「すぐには役に立たない」ものこそが、本当に大切なものだと考えています。
長期間を掛けて成長する大木のように、確かな土台を身に着けていきたいものです。
おすすめ①「小商いのはじめかた」 伊藤洋志 著
小商いは、個人で行う身の丈にあった商売の事を指します。
「起業=一部の人にしか出来ない」
と思われがちですが、商店街にあるお店だって起業形態の一つに過ぎません。
起業は特別なものではなく、ごくありふれたものである。
違うのは、規模やスケールだけ。
ですので、誰にでも身の丈にあった小商いをすることは可能なんです。
現代のようにテクノロジーが発達しつつある環境では、一段と個人ビジネスの敷居は低くなっています。
本書の著者である伊藤さんは、数多くの職業を掛け持ちし、”百姓”のような仕事をしています。
(百姓というのは、百の仕事、つまり沢山の仕事を持っている人を指します。)
彼から、他職の流儀を学んで生き方の参考にしませんか?
百姓のような生き方については、以下の記事でも触れていますので参考にしてみてください。
>>仕事は複数持つのが当たり前の時代へ 単職から多職への転換期
「僕たちは就職しなくてもいいかもしれない」 岡田斗司夫 著
を題材にしています。
おすすめ②「完全版 社会人大学人見知り学部 卒業見込」 若林正恭 著
オードリーの若林さんのエッセイです。
若林さん独自の視点や鬱屈とした感情を抱える人に対する、応援本になっています。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
>>人見知り芸人、オードリー若林 ネガティブを潰すのは没頭しかない!
おすすめ③「脱社畜の働き方 ~会社に人生を支配されない34の思考法~」 日野瑛太郎 著
(2025/08/31 22:39:49時点 Amazon調べ-詳細)
本書は「脱社畜ブログ」を運営されている、日野瑛太郎さんの作品です。2020年以降(2022/3月現在)更新がありませんが、「働き方」や「労働観」について問題提起を行う革新的なブログを運営されています。
本書を読むコトで、「働き方」について深く考えることができるようになります。
詳しくは以下の記事に記載しています。
>>「精神的脱社畜」には会社を辞める必要なんてない | 『脱社畜の働き方 日野瑛太郎 著』
おすすめ④「内向型人間の時代 社会を変える静かな人の力」 スーザン・ケイン 著
内向的で控えめである人たち。
本書はそのような人間こそ、本当に強く、これからの時代にとって必要だということを主張します。内向型はあくまで性質であって、人間の思考や行動のパターンでしかありません。それぞれの特徴を知ることで、他者とのコミュニケーションをスムーズに進められるようになるでしょう。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
>>“内向型”は欠点ではなく長所です | 『内向型人間の時代』スーザン・ケイン著