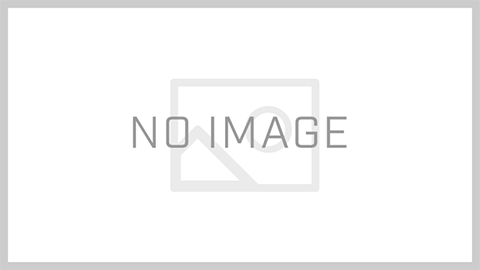近年テレビを見ていると、若い世代の活躍が目立ちます。
卓球では張本智和選手が史上最年少で日本一となり、フィギュア界では羽生結弦選手が脚光を浴びています。
これは、若者の一人である自分としても喜ばしいことであり、もっと様々な分野で新しい風に活躍して欲しいと願っている次第です。
ところで先日”情熱大陸”を見ていると、日本人の青年がカンボジアで紙を作り、雇用を生み出しているという特集がなされていました。
山勢 拓弥さん:第50回 社会貢献者表彰 受賞者紹介
カンボジアには、世界遺産”アンコールワット”があります。
旅行者が選ぶランドマークランキング2015で一位を獲得するほどの人気スポットであり、カンボジアの象徴だと言えるでしょう。
しかし、その裏にはゴミ山で働く人たちの存在がありました。
ゴミ山の中から、再利用できる空き缶やペットボトル、鉄くずなどを売って生計を立てている人がいるのです。
ゴミ山に運ばれてくる廃棄物は、一般ごみや産業廃棄物、医療廃棄物を含んでおり、常に危険と隣合わせの環境です。
地盤が崩れれば、最悪の場合は死に至るような劣悪な場所。
けれども生きていくためには、そのような場所で働くしかない人達が大勢いるのです。
この環境を何とかしたい。
そう思った山勢拓弥(1993年生まれ)さんは単身カンボジアに渡り、バナナで作られた紙、通称“バナナペーパー”を製造する財団を営んでいます。
どのようなきっかけで海外に行くことになったのか?
そして、なぜ日本ではなくカンボジアなのか?
その理由が興味深かったので、書き残しておきたいと思います。
優等生の挫折
小中高と活発な子どもだった山勢さんは、高校時代には、サッカー部のキャプテンとして結果を残すとともに、成績も優秀で、有名私立大学の推薦を受けます。
しかし、サッカー部の陰口を叩かれたことが喧嘩に発展し、相手に怪我を負わせたため、推薦取り消しに。
受験で大学を受けざるを得なかったという挫折を味わっています。
大学入学後の1年生の春には、母親の友人が行っていたボランティアに誘われ、カンボジアで古着配りをすることになります。
その後、現地人と知り合いになり、カンボジアの現状を知っていくにつれ、なんとか現状を変えたい気持ちになったんだそうです。
その後、大学1年の冬には、学校を中退し、カンボジアに渡るというわけです。
カンボジアに行ったのは”ほんの些細なきっかけ”だった
カンボジアに渡ったきっかけ。
それは”ボランティアに参加した”という些細なものでした。
しかし活動に取り組んでいくうちに、今まで見えていなかったものが浮かび上がってきて、居ても立ってもいられない。
僕自身も、新聞や本を読む中で、”なんとかしなければいけない“、と感じる事柄が山ほどあります。
けれどもそう思うのは一瞬であり、継続して気持ちを維持するのは難しいと感じています。
貧困に喘いでいる人がいれば可愛そうだと思い、無茶苦茶な政治には怒りを感じる。
何も行動に起こすことはできずに、ただ想っているだけ。
カンボジアの現状を知り、現地に飛んでしまえる”フットワークの軽さ”と”行動力”は本当に尊敬します。
一体なぜ”バナナペーパー”?
カンボジアの人たちの暮らしをよくしたい。
その気持ちだけでは、何も変わりません。
重要なのは、”暮らしを支える基盤を築く“こと。
つまり、お金を生み出すことです。
そこで山勢さんが選んだのが”バナナペーパー”でした。
他にも色々商材はあるはずなのに、なぜバナナペーパーなのでしょう?
ゴミ山に関わっていて、ゴミを出さずにって考えたことはなかったのですが、日本語で書かれたゴミもあったり、市内でよく使われているものがあったりするんです。
ゴミの墓場がゴミ山なのかな、ではゴミの墓場をどうしていこうかなと考えていったときに、自然のものを使って何かを作りたいなという気持ちはすごくありました。
そんなことを色々な人に話していたら、あるときバナナペーパーの存在を教えてもらったのです。
バナナペーパーは、カンボジアでは初なんです。
どこにもない素材っていうことで評価は受けていますね。
ゴミをゴミとして終わらせるのではなく、ゴミを”商品”にリサイクルしてしまえ!という発想。
自然を大切にしたいという想いを持ち続けたからこそ、辿りつけた答えなのでしょう。
カンボジア国内では、初めての素材ということで、非常に高い評価を受けているそうです。
こちらのページで販売もされているそうなので、興味のある方は覗いてみてください。
オンラインショップ
>>Ashi|亜紙
日本は豊かだけれども、何かが足りない
カンボジア人のために単身海外へ渡り、しかも事業を立ち上げる。
人々の暮らしを良くしたいという貢献心があり、意識まで変えていく存在。
そんな彼は、誰をロールモデルにしていたのでしょうか。
山勢さんが、影響を受けた人物として挙げているのは、NPO法人ロシナンテスの代表です。
こちらはスーダンで医療貢献をしている団体になります。
高校時代にたまたま、その代表が講演に来てくれたコトで考え方が一変したのだとか。
ちなみに語っていた内容というのは、
その人が講演で言っていたのは、「日本には何でもあるけど、何かがない。スーダンには何もないけど何かがある。」
スーダンという国のことはよく知らないけれども、何かがある。
それは実際に行ってみないことにはわからない。
それに対して日本には物が溢れているけれど、何かが足りない。
それは一体何なのか?
この対比による違和感が、山勢さんをNPO活動へと駆り立てるきっかけとなったんですね。
僕自身もスーダンとは言わずとも、海外に行ってみて、日本との違いを改めて確認してみたいと感じました