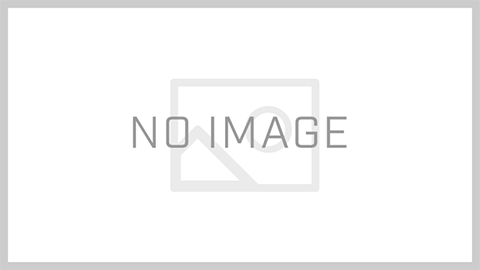- 小学生
- 中学生
- 社会人
- 大人
僕たちは、いつも何かに括られています。
例えば生まれた時には「赤ちゃん」というラベルを付けられ、大きくなるに従って「大人」へと成長する。
そんな方が大半だと思います。
では「大人」って一体何でしょう?
何となくのイメージはできても、「こういうものだ!」と言い切れる人は少ないのではないでしょうか?
そう、大人の定義って曖昧なんです。
今回、神戸女学院大学の名誉教授である、内田樹さんの書いた書籍「期間限定の思想 「おじさん」的思考2 (角川文庫)」を読みました。
本書に「大人とは何か?」が書かれていましたので、ご紹介したいと思います。
すでに答えは出ている
「大人ってどういうことですか?」
その質問をした人は、すでにその答えを知っています。
この問いかけの内には二つの言明がすでに含まれている。
ひとつは「私は子どもです」。
ひとつは「あなたは大人です」だ。
「どうして、そういうことになるんですか?」
だってそうだろ。
「・・・とはどういうことですが?」という問いは、ふつう「答えを知らない人」が「答えを知っているはずの人」に向ける言葉だからだ。
そして、「誰かが、自分には解けない問いの答えを知っている」と考えること、実はこれが「子ども」の定義なのだ。
そして、「子ども」が「答えを知っていると想定している人」のこと、これを「大人」と呼ぶのだ。
質問を投げかけている人は、相手のことを「答えを知っている人」と判断して質問しています。
この時点で相手を大人だと判断していることになるんですね。
「大人」は「子ども」によって作られる
大人とは、
- お金を稼げる人
- 知識の豊富な人
- なんでも一人でできる人
といった定義をされることがあるかもしれません。
でも大人って、そういった言葉で決められるものではないんです。
「大人」とは「子どもから大人だと思われている人間のことである」
これに尽きる。
「大人」は「子ども」との関係の中にある種の「水位差」としてしか存在しない。
誰かに「大人だ」と承認されない限り、「大人」は存在しない。
「大人」というのは、「子ども」から「大人になるにはどうすればいいんですか」と問いかけられた当のその人のことなのだよ。
とても厳しい意見ですね。
「子ども」から認められて初めて「大人」になる。
つまり反対に考えると、「子どもが認めない = 大人ではない」ということになります。
大人になってしまった。
そう思っていても、実際には大人になり切れない子どもが沢山いるのかもしれません。
「答えを知っている者はいない」と考えるのが大人
先ほどのお話しでは、「子ども」が「答えを知っている人」と認めた人が大人ということでしたよね。
ではどうすればそんな大人になれるのでしょう?
そのためにはまず「子どもとは何か?」について、考えてみなければなりません。
内田先生は次のように言っています。
「子ども」は、説明できないことが起こると、その原因を「私の外部にある強大なもの、私の理解を超えたもの」、つまり「あらゆる問いの答えを知っているもの」に帰着させようとする。
「誰かが全部裏で糸を引いているんだ」。
そういうふうに考えること、それが「子ども」の危うさだ。
問題の原因は、誰かが裏で手を引いている。
そんな風に、常に「誰かのせい」と考えてしまうのが「子ども」だと言っています。
日本は「大人」がいない国になっているかも
現在、日本では少子高齢・年金などの課題が山積みになっています。
本来であれば、協力し合うべき政党はお互いをののしり合い、蹴落とそうとばかりしています。
そして私たち国民も政治家を批判し、悪の根源のように思い込んではいないでしょうか?
しかし今回の話から考えると、私たちが「子どもだから」そのように考えてしまうのかもしれません。
大人であれば外部のせいにせず、まずは自身の行動から始めるはずだからです。
そうすれば、子どもからも認められる立派な大人になれるでしょう。
最後に
- 「大人って何?」。その質問をした時点で「大人」が何かを知っている
- 「大人」とは「子どもから大人だと思われている人間のこと」
- 「子ども」は誰かが答えを知っていると考える
今回は内田樹さんの本を紹介してきました。
この「期間限定の思想 「おじさん」的思考2 (角川文庫)」は、悩みごとを持っている人に、僕がよくオススメする本です。
この本には、”仕事”・”結婚”・”社会”といった様々なトピックについて独自の視点で語られています。
きっと皆さんの心にも響く言葉があるはずです。
ぜひ一度、読んでみて欲しいです。