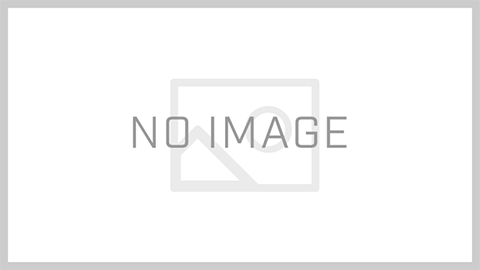- 「働く = 社会と繋がる」こと
- 居場所を手に入れるために
- 道を切り開くためには、「自分の頭で考える」
先日、『「働きたくない」というあなたへ』という、書籍を読みました。
作者は山田ズーニーさん。
全国各地をまわって表現活動・コミュニケーション力の育成など幅広く活動されています。
- 読者のお便りを掲載
- ズーニーさんがお便りに回答する
本書はこのような構成になっています。
読者の意見を脚色することなく、「本を読んでくれた人」にありのままを伝える。
学生・主婦・高齢者といった幅広い年齢層のさまざまな背景を持った人たちの、本音が垣間見れたのは非常に面白かったです。
本書では一貫して、
働くとは、社会と繋がることである
と主張しています。
それぞれの立場は違っても、「人や社会と繋がりたい」という気持ちは誰もが持っています。
「働くこと」を通じて、私たちは、人と社会と繋がっていけるのです。
私たちは「へその緒」を通して、社会と繋がっている
著者のズーニーさんは、出版社で勤めた後、フリーランスとなりました。
そこで初めて自分は
会社を通して、社会と繋がっていた
と実感したそうです。
思えば小学校・中・高・大学と、箱が、社会と繋がっていた。
チューブを通して栄養が補給されるように、「へその緒」を通して、社会から、必要な情報も、信頼も、与えられ、守られてきた。
あまりに当たり前に「居場所」が与えられる生活をしてきたので、自分の手で「居場所」を失うと、
狭い箱に閉じ込められたように、とたんに「不自由」きわまりない生活になった
学生の頃は、自動的に「居場所」が与えられていました。
「○○学校に通う○○君」
「△△組の△△さん」
それらは、自分の意志で獲得した居場所や肩書ではなく、社会から勝手に与えられたもの。
「規則」や「しがらみ」という不自由がある一方で、学校や会社という枠組みを通して、私たちは「社会」と繋がるコトができたのです。
それらを失ったことで、ズーニーさんは、「社会との繋がり」が失われてしまったと感じたそうです。
居場所がなくなると、繋がりも失われる
この意見には、僕にも共感できる所があります。
僕自身、以前に勤めていた会社では、様々な人と繋がることができました。
飲み会に参加したり、一緒に仕事をしたり、たくさんの仲間ができたような気分でいました。
しかし会社を辞めると同時に、多くの繋がりは失われてしまったのです。
平日の昼間にはもう、一件の電話も鳴りません。
誰も自分自身を必要としてくれる人はなく、日々社会から忘れさられ、干されたような気分でした。
今まで「個人」で繋がっていたと思っていた関係は、「会社」を通して繋がっていた関係にすぎなかったと気づかされたのです。
一旦所属を離れると、肩書や役割がなくなり、相手との接点は薄くなっていく。
そして、気づいた時には誰もいなくなっているのです。
よく定年後の男性が、社会から孤立してしまうと言われます。
それは会社という「居場所」を失い、むき出しの個人になってしまうからなのです。
人は誰かに必要とされ、貢献することで、勇気と希望を持って、前向きに生きていくことができます。
失って初めて、その辛さを思い知ったのです。
居場所がなければ、そこに「自由」はない
自由な働き方として、
- フリーランス
- ノマドワーカー
という言葉が注目を浴びました。
場所や時間に縛られず、自分ですべてを自由にコントロールする。
そのような働き方に憧れる人が多いのでしょう。
もしかしたら、「働きたくない」から、自由な生き方に惹かれるのかもしれません。
しかし
- 働きたくない
- 仕事したくない
という思いを抱いたまま、本当の「自由」は得られるのでしょうか?
それに、次なる「居場所」はどうやって手に入れるのでしょうか?
学校に属さず、就職もしないとなると、自分で次のアクションを起こすしかありません。
居場所は、自らの行動の先にしか訪れません。
そして、「自分と社会をダイレクトに繋ぐ」のは難しいことかもしれません。
「私は○○というものです」という剥きだしの看板を頼りに、社会と繋がる。
それは「私の人間性や能力」と、直に向き合うことを意味します。
今までは存在した「○○会社の○○さん」といった、自分を守ってくれた、会社という盾はありません。
仮に相手から否定された場合、会社ではなく「自分自身」が否定されることに直結します。
何かに所属するためには、エネルギーが必要です。
働きたくないといった所で、私たちは「居場所」や「愛」といった生きていくための養分を取り続けなければなりません。
「働きたくない」という人は、もう一度
自分にとって、最良の社会との繋がり方は何なのか?
を考えてみてはどうでしょう。
「希望」はどこにあるのか
テレビの特集で、「近年、将来に対して希望を持てない若者が大勢いる」という報道を目にしたことがあります。
その回答として納得したお便りがあったので、ご紹介したいと思います。
じぶんが動けば、なにかが変えられる」と思っている人は、魅力的に感じられるのかもしれない。(省略)
いまって、日本中が、なんとなく、
「昨日とちがう未来」なんかないんじゃないか、
いやもっと悪くなるんじゃないか、というムードです。
そういうなかで、ほんのちょっとだけど
「じぶんが動けば、なにかが変えられる」
と思っている人の周囲は、やっぱり変わっていくんで。
働くことや将来に、夢や希望を抱くことが出来ない。
そう感じてしまうのは、
自分が頑張った所で、何も変わらない
という考えには、ハッとさせられてしまいました。
なぜなら、僕も同じ想いを抱いたことがあるからです。
例えば、会社で仕事をしているとき。
自分が仕事を頑張らなくても、普段と変わりなく組織は回ります。
それは組織の規模が大きくなるほど顕著であって、一人ひとりの力は小さく、個人には大きな影響力がないことを意味します。
何かを変えたくても、大きな力に巻き込まれて身動きが取れなくなっていく。
そして次第に、
自分が動いた所で仕方がない
という気持ちが深まっていったのです。
今、将来に希望を持てないと思っている若者の多くは、同じような気持ちを抱いているのかもしれません。
現状を変えたいけれど、どうすることもできない。
自分が頑張った所で、何も変わらない。
そんな無力感で、一杯なのかもしれません。
私たちは、本当に未来を変えられないのか?
でも本当に、私たちは無力な存在なのでしょうか?
ズーニーさんは、決してそんなことはないと言います。
「自分の頭で考えて物事を決める」と道は開けてくると言うのです。
自分で決めず、人に付いていくから、いつまでたっても自分のものにならないのです。
なんとなく周りに流されて、人生を他人に預けてしまうから、一生不満を持ったまま生き続けることになってしまう。
たとえ、個人の力は小さくても、自分の決めたことを言葉にして、行動に移していく。
周囲と本音でぶつかって、結果が出なくても失敗を引き受ける。
将来に希望を持てるかは、こうした小さな一歩を積み重ねるしかないのです。
最後に
今回は、少ししかお便りをご紹介することが出来ませんでした。
けれども書籍の中では、本当に多くの方々が「働く」に対する意見を投稿されています。
みなさんも経験があると思いますが、身近な人に「働き方」の相談をすると、大抵似たような回答が返ってきます。
- 働くのは当たり前
- つべこべ言わず働け
といったように。
でも本来は、一人ひとり「働く」の考え方は違っていいのです。
社会どうやって繋がりたいかを考える
自身を見つめ直すことで、心の底でくすぶっていた想いが湧き出てきます。
本書を読めば、一辺倒の意見ではなく、「自分にしっくりくるアドバイス」が見つかるはず。
ぜひ、一度読んでみて欲しいです。