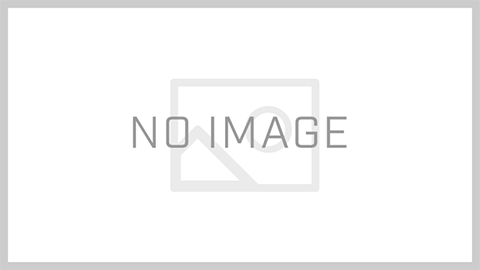身の回りの情報が多すぎると、人間は疲れてくるのかもしれません。
必要・不必要な情報を取捨選択すればいい
そのような問題ではなく、単純に情報のシャワーを浴びすぎると、周囲に影響を受けすぎて、自分が分からなくなります。
今そのような人が、大勢いるんじゃないかと感じています。
インターネットに常時接続している、つまり「スマホやパソコンが自分の体の一部なんじゃないの?」と錯覚するような現代社会において、私たちはどうやって情報に接すればいいのだろう?
この記事では、以下の内容をご説明していきます。
- 情報との付き合い方
- 無駄を省いてはいけない
- ネットには存在しない”ノイズ”の大切さ
情報はネットで仕入れるべきなのか?
インターネットが存在しない1990年以前では、情報を手に入れる方法は、
- 本
- ラジオ
- テレビ
- 人から直接教えてもらう
これらが一般的でした。
しかしネットが登場して以降、「情報はネットから仕入れるものだ」という認識が、頭の中にインプットされ始めたと感じています。
- 分からないことを質問すると、「ググればいいやん」
- 目的地への道順が分からないなら、「Googlemapで検索すれば?」
このようなやり取りが、当たり前のものとして浸透しています。
これは「人に頼るよりも、機械の方が信頼性が高い」ことを意味しています。
機械を信頼すればするほど、私たちは他者から情報を得る機会が少なくなります。
会話の量が減ってしまうからです。
人を頼る過程で生まれるコミュニケーションが、次第に省かれてしまうのです。
機械の正確性を信仰しすぎるあまり、人間という不正確な存在を認められなくなる。
これは「人間の限界は機械の力で乗り越えられる」と錯覚する、あわれな人間の心を現しているようです。
ネットの情報からは”体験”が得られない
ネットで情報を手に入れるのは、非常に簡単です。
興味のあるキーワードで検索すれば、気になる情報がいくらでも手に入ります。
しかもそれは日本に留まらず、世界中のありとあらゆる情報が。
- 今まで知らなかった土地
- 食べたことのないフルーツ
- 見たこともないような生物
それらは写真や動画、あるいは文字というツールを媒介として、リアリティを伴って、私たちの元にやってきます。
その結果、私たちは「この世のものは、インターネットからすべて得られる」のだと錯覚してしまいます。
家の中から動かずして、「世の中のあらゆる知識を手に入れ、経験ができた」と感じてしまうのです。
ネットには、人間にそう思わせるだけの力があります。
無駄を省かず、ノイズを受け入れる
ただし、ここで注意が必要なのは、「“机上の知識”と”経験で得た知識”は異なる」という事実です。
例えば富士山を写真で見るのと、現地で見るのとでは、情報量が異なります。
なぜなら現地で見る富士山には、様々な要素が付加されるからです。
写真では感じられない、澄んだ空気や草木の匂い。
現地の人たちとの何気ないふれ合い。
そうした多数のパラメーターが入力されると、科学反応が起こります。
同じ場所へ行ったのに、人によって得られるものは全く違う。
それは”入力されたインプット“がそれぞれ異なるからです。
同じ富士山でも、現地へ行けば思わぬノイズが入力されます。
その結果、「富士山を見た」という経験が新しい輝きを放ち始めるのです。
哲学者である”東浩紀氏”が『弱いつながり』で指摘するように、現地へ自分の足で赴き、肌感覚で感じることが大切です。
つまり、検索というショートカットを使わずに、無駄を受け入れることが大切だということです。
図書館に行って棚で本を探す。
この一見すると無駄な途中の過程、これこそが「経路」です。
実はその経路の途中で、何か発見があることが多いのです。
だから、検索によって経路が無くなると、人間のクリエーティビティーは下がるのではないかというのが僕の根本的な問題意識です。
これはジャック・デリダの哲学から来ているのですが、僕の生理的な感覚でもあります。
僕はカーナビもニュースキュレーションサービスも同じように「経路」が無くなるので好きではありません。
カーナビで目的地まで走るよりは、カーナビに頼らず自分で調べながら運転したい。
ニュースキュレーションにしても、毎日新聞なら毎日新聞のサイトに行ってクリックするという経路が大事なのです。
そこで目的の記事以外をクリックする可能性があるからです。
事前に登録した記事だけが自動で配信されてきても、それ以上の発展がありません。
情報との向き合い方
インターネットは「自分のみたいものしか見られない構造」になっています。
TwitterやFacebookにしたって、すべては自分の好みで取捨選択が行われた上で、情報が入ってきます。
そのため、いつの間にか「自分に都合のいい情報ばかり」を受け取ってしまうのです。
気づかない内に、都合の悪いことには目をつぶる。
臭いものには蓋をして、存在していないものと同義に扱う。
私たちは情報が固定化されるほど、繋がりを強固にしてしまいます。
そして、多様性や個人を認められなくなるのです。
一人ひとりがインターネットに接続しているならば、「自分と情報との関係性」を意識することが重要です。
「胃の中の蛙」にならないためにも、情報との距離感は意識したいものです
ネットに接続していないと、落ち着かない
インターネットに常時接続していると、「接続していない状態が異常」だと感じてしまいます。
そのようなネット中毒者のような症状を、感じることがあります。
次々と更新される情報のシャワーを浴び続ける。
留まることのない、他人の動向や意見に耳を傾けていると、飲み込まれそうになってくるのです。
- 他の人はこれだけ頑張っているのに、自分なんて…
- なぜ失敗ばかりしてしまうんだ…
成功している人や、上手く行っている人と比較することで、自分を卑下してしまいます。
実際の所、SNSで投稿をしている人の多くは、「上手くいった・成功した・幸福だ」といった、ポジティブな感情だけを更新しているのだと思います。
そこには、
- 人から良く思われたい
- すごい人だと思われたい
- 注目されたい
といった、人間の持つ”自己顕示欲”が潜んでいます。
ですので本来は、そのような情報を気にする必要はないのです。
もし気になるようなら、一度情報をシャットアウトしてみるといいのかもしれません。
情報を遮断する勇気
私は情報を遮断することで、「気持ちの良い1日」が送れると感じています。
数時間でもいいので、携帯やパソコンの電源を切ってみる。
あるいは、外に出て日の光を浴びながら、自然の中に身を置いてみる。
すると、いつもは感じることの出来なかった、虫たちの声や川の流れる音色が聞こえてくるのです。
毎日機械に触れていると、人間が持っている”肌感覚”が鈍くなるのかもしれません。
自然と接すると、”生きること”を実感できます。
スーパーで売っている肉や魚、あるいは育てられた野菜たち。
それらは自然からの恵みだと言えるでしょう。
けれどもそれらは、下処理が施され、自然本来が持つ”野生”が取り除かれた上で、陳列されています。
直接的に、自然と接しないことで私たちは”自然”を感じる機会が減っています。
それも人間の感覚が鈍くなっていることに影響しているのかもしれません。
人間も他の生き物と同様、地球という星に生まれた生命の1種類に過ぎません。
情報と切り離されることで、私は”自然の中で生きている”ことを思い出せるのです。
最後に
今回は最近感じている、「情報との付き合い方」について考えてみました。
無限に広がる大海原のように、情報は日々増え続けています。
昔のように「欲しい情報が足りない」のではなく、「情報がありすぎて選別出来ない」状況へと変化しています。
それは確かに豊かなことではあるけれど、知らずしらずの内に私たちの首を絞めているのかもしれません。
- 知ってしまったがゆえに、行動を起こせなくなる
- 情報を取り入れすぎたために、何が正解か分からなくなる
このような状況に、陥ってしまうからです。
有名人たち(例えば、ホリエモン)は、「情報のシャワーを浴びろ!」と訴えかけてきます。
成功者に言われると「自分もそうしなければ」と思うかもしれませんが、一度立ち止まって考える必要があるのではないでしょうか?
本当に大切なことは、「自分の頭で考える」ことです。
情報を下地にすることはあっても、何の加工を施すことなく、自分に当てはめてはいけません。
人それぞれ違うのですから、自分に合うように加工する必要があります。
その上で、血肉と化していくのです。
たまには情報を遮断しながら、あるいは吟味しながら自分用にアップデートしていきたいものです。