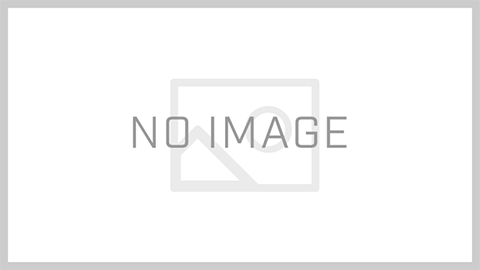従来の日本企業は、社員が「副業」を行うことを認めていませんでした。
しかし終身雇用の崩壊・賃金の低下といった社会変化によりその方針が変わりつつあります。
この記事では、以下の2点を中心にご説明していきます。
なぜ副業は禁止されてきたのか?
なぜ副業解禁の流れが出てきたのか?
そもそも、なぜ副業は禁止なのか?
日本には「モデル就業規則」というものがあります。
その中の服務規律第11条に以下の規則があり、 副業禁止の要因になっています。
「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」
参照:厚生労働省モデル就業規則
この条文を企業が参考にしたため、「副業を原則認めない」という状況になっていたのです。
政府が副業を容認する流れに
しかし2016年12月26日、厚生労働省が掲げる「モデル就業規則」において、副業規定を廃止し、副業を「原則容認」にするという発表がなされました。
就業規則のモデルで副業規定を廃止するということは、「国が副業を認めた」ことになります。
副業を禁止され、二足の草鞋を履けなかった労働者にとって、大きな転換機を迎えたことなるでしょう。
社会は変化しようとしている
終身雇用の崩壊や賃金の低下といった社会変化により、少しずつ社会に歪みが出始めています。
大企業に入れば一生安泰という時代ではなく、企業の平均寿命は23.5年(参照:東京商工リサーチ)というデータも出ています。
20歳で就職したとすると、定年を迎えるまでは約40年です。
この計算でいくと会社勤めをしている場合には、定年までに約2回の倒産を経験することになります。
そう考えると、非常に恐ろしいです。
なぜ解禁の流れになったのか?
そのような状況においては、”最悪の状況に備えよう“という意識が大切なのだと思います。
副業解禁で国民に期待されていることは、「リスクヘッジをお願いします」ということです。
1社でダメなら2社、あるいは自分で事業を起こすなりして資金を作ってくださいね、という意味なのだと感じています。
また副業解禁の狙いとして、世耕経済産業大臣は以下のようにも語っています。
企業は、話題の副業解禁を増やしていくべきでしょう。
もちろん、健康管理は前提条件です。
しかし副業は、視野の拡大や、 新しい価値観の入手、新たなビジネスへの可能性にもつながります。
その結果、これまで日本企業全体の課題でもあった「人材の低流動性」を解決する手立てにもなりえるのです。
なるほど。
他国に負けない価値を作りだし、人材の流動性を高めたいという思惑もあるんですね。
副業解禁、デメリットはあるの?
副業解禁の流れは、一見すると労働者にとってメリットが多いように思えます。
しかし、物事には必ずメリット・デメリットが存在します。
1つ目のデメリットは「労働時間が伸びる可能性」です
サラリーマンの賃金は年々下降の一途を辿っており、その賃金の穴埋めをするために副業の存在が期待されています。
そのため、例えば会社の残業代で稼いでいた人は、その残業分を他の収入源で補わなくてはなりません。
方法としては、自分でビジネスを行ったり、バイトをしたりなどがありますが、今までもらっていた給料を手に入れるためには余計に労働時間が伸びる可能性があるのです。
2つ目は「格差が広がる可能性」です。
今までは規則のために抑えられていた、”優秀な人”が副業を始めます。
彼らはアルバイトのような低賃金ではなく、起業したり、他者からの業務委託を受けるなど、高収入の副業をするかもしれません。
そうなった時、自分でビジネスを起こせるような”スキルを持った人”と、”何のスキルも持たない人”の間に大きな格差が生まれる可能性があります。
副業をOKにしている会社
2016年6月には先駆けて、「ロート製薬」が副業を解禁する動きを見せ始めました。
リモートワークが可能であるIT系の企業ではなく、技術流出を恐れるメーカーにおいて、このような動きが出たことは、今後大きな変化に繋がっていくはずです。
そして副業を容認する会社は他にもあり、例えば以下のような会社は副業OKとされています。
ロート製薬
サイボウズ
リクルート
ヤフー
サイバーエージェント
名だたる企業ですでに容認されているみたいですね。
果たして今後はどのような流れになっていくのでしょうか。
最後に
副業解禁によって、人材の流動性は高まっていくでしょう。
また副業のお陰で、「新たな価値を生み出すビジネス」の生まれる機会が増えると思われます。
一方で格差は広がり、労働時間が伸びる可能性は否定出来ません。
メリットだけではなくデメリットも考慮して、今後の「働き方」を一人ひとりが考えていかなければいけないのかもしれません。