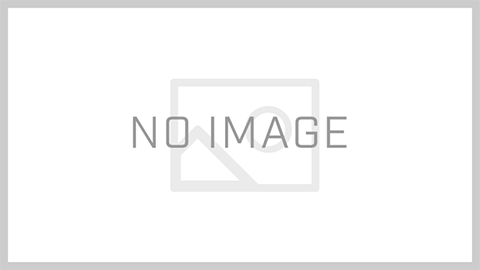- 人は「学ぶ」ために、「真似る」ことを繰り返す
- 個性を発揮するために必要な考え方
- 自分のたどり着きたい場所を考える
「学ぶ」という過程の中には、「真似る」が含まれていることが往々にしてあります。
なぜなら、真似ることを繰り返す中で人は学び、知識や技術を手に入れていくからです。
真似ることは、学習のスタート地点。
言葉を話すのだって、記憶にないだけで、家族や他者からの声を聞いているうちに話せるようになったはずです。
人は生まれながらにして、「真似る」ことを通じて、学習していくのです。
「真似る」ことは「学ぶ」こと
たしかに人は「真似る」ことを通じて、学んでいきます。
ということは自分のオリジナリティを出したいといっても、それらはすべて模倣に過ぎないのでしょうか?
一体、個性はどこにいってしまったのだろう?
感覚的に、「個性」を発揮するためには、真似ることを繰り返し、そこにアレンジを加えていく必要があるように思います。
「守・破・離」と呼ばれるように、まずは基本を「守った」上で、学んだ基礎を「破り」、オリジナリティを出すためにその場から「離れていく」といった過程を辿るのでしょう。
「守・破・離」
- 基本を「守る」
- 学んだ基礎を「破る」
- その場から「離れる」
「素直」と「反抗」のバランスが重要
まず初めに立ちふさがる「守」の段階では、強い「忍耐」が必要になってきます。
真似るためにはお手本となる誰かが必要になりますし、時には教えを乞う必要もあるでしょう。
その際、教えられたことを「はい、やります!」とすべてを受け入れられるといいいけれど、時には「なんでこんな事が必要なんだ?」と思うことも出てくるはず。
教えられていることが必ずしも正しい保証はないし、師匠と弟子との関係性は、ある種の信頼関係でしか成り立ちません。
ただ、素直に師匠の言うことを聞けば成功するかといえば、それも違います。
言われたことを受け入れ続けていても、「離」の段階からは抜け出せないだろうし、反発しすぎれば、今度は「守」の力が十分身につかないかもしれません。
要は、素直と反発のバランスが大切なのでしょう。
その過程を経て、人は一人前に近づくことができるのです。
守・破・離の先にある「プロ」
一人前というのは、ここでは「自身で立つことができる」という意味です。
つまり、その道のプロです。
例えば、
- プロ野球選手はプレー
- デザイナーは描いた絵
の対価として収入を得ます。
高い専門性と技術を手に入れることが、プロがプロとして扱われる所以であり、ほんの一握りしかその場に辿りつくコトが出来ないからこそ、人々は彼らに称賛を与えるのです。
仮に簡単にその地位へ辿りつけるのなら、それはもうプロではなく、プロの顔をした凡人に過ぎないのです。
とはいえ、必ずしもプロにならないといけないワケではありません。
すべての人が特定の道で生計を立てられるはずがないですし、「守・破・離」自体を意識する必要のない道もあります。
別に「離れなくても」、「身を立てられなくても」、自分らしさや個性を生み出せる可能性もあるのです。
それは例えば、趣味で絵を描くことであり、料理をすることだってそう。
趣味の範疇で、好きなことを自分の望むやり方で表現することが個性に繋がるということです。
「趣味としての自分らしさ」と「プロとしての個性」
ただ、ここで一つだけ注意が必要なのが、「趣味」としての「自分らしさ」は活動の幅が狭くなってしまうということです。
個性はあるかもしれないけれど、それは所詮、大多数から頭一つ抜き出ているに過ぎません。
周りが追随してくれば、その「自分らしさ」という差異は簡単になくなってしまいます。
それに引き換え、「守・破・離」を経て手に入れた「個性」は、容易に手に出来ない奥行きを持っており、その場に辿りつくコトが困難です。
幅広い知識を教養として扱えるようになるために多大な時間が必要なように、その「個性」を得るまでには時間がかかる。
一部の人にしか到達できない領域になります。
一体どこへ行きたいのだろうか?
結局何が言いたいのかというと「自分のたどり着きたい場所」を考えようよ、ということです。
趣味としての「自分らしさ」か、あるいは「身を立てるための個性」のどちらが欲しいでしょうか?
前者であれば、恐らくすぐ手に入るはずです。
でも、すぐに陳腐化し、その「自分らしさ」はコモディティーという大海に飲み込まれてしまう。
一方、後者が欲しいのならば、「守破離」の道を経なければなりません。
その道は困難であるし、限りなく狭い道であるという覚悟も必要でしょう。
ただ、すぐに周囲に飲み込まれることはなく、大抵の人間はその場に到達するまでに脱落していくはずです。
どちらにたどり着きたいのか。
まず目標地点を考える必要があるのでしょう。