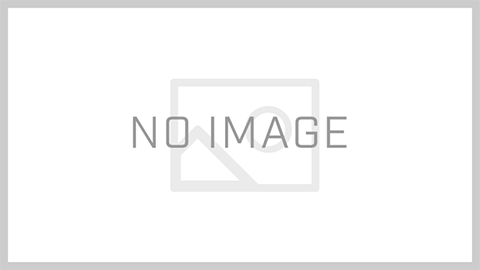- 「暇そうな不動産屋」が潰れない理由が知りたい
- 儲けのカラクリ
日本の人口は減少の一途を辿っています。
それに比例して、不動産は需要が減っているのに加え、高齢化社会の影響を受けて「空き家」が増えるという負のスパイラルに突入しています。
総務省が5年ごとに公開している「住宅・土地統計調査」によれば、2013年の全国の層住宅数は6063万戸。
その内なんと820万戸がすでに空き家(空き家率は13.5%)になっているとのこと。
参照:平成25年住宅・土地統計調査(速報集計)結果の要約
これでは不動産屋は堪まったもんじゃありません。
借りたい人はいないし、家賃も下がっていくし八方ふさがりじゃないかと。
けれども、町にある不動産屋を思い浮かべてください。
どうみたってお客さんの姿は見えないのに、なぜか潰れない店舗。
どうやって儲けを得ているのか不思議ですよね?
実はそれには知られざる儲けのカラクリがあったのです
https://it-information-engineering.com/store-karakuri
https://it-information-engineering.com/why-not-crushed
不動産屋の収益パターン
不動産屋の主な業態は以下の3つです。
- 不動産の売買仲介
- 不動産の紹介業務
- 不動産の管理
売買ならば、物件価格の3% + 6万円 + 消費税が手数料収入です。
賃貸ならば、紹介物件の1か月分の賃料相当分が手数料収入です。
参考文献:価格と儲けのカラクリ(p126)
それでは、一つずつ説明してきましょう。
不動産屋の仲介って?
不動産の主な仕事内容が、「物件の仲介役」になることです。
これは不動産を
「売りたい人と買いたい人」
「貸したい人と借りたい人」
とをマッチングさせることで、仲介料(手数料)をもらう仕組みになっています。
仲介料をもらって事業が成り立っている業態は意外と多いです。
例えば、商社は仕入先から売り先への中間に立って手数料を稼ぎますし、結婚相談所にしたって、「婚活パーティ」という場を提供することでお金を稼ぎます。
ただし、この不動産仲介業では安定的な収益は見込めません。
なぜならお客さんの
- 見込める時期
- 見込めない時期
が発生するからです。
年間を通してみると、事業として上手く成り立たせるのはなかなか難しいのです。
忙しい時期だからといって、必ずしも「仲介役」が出来るわけではありません。
お客さんを見つけないことには、物件の仲介が出来ませんし、自分のお店で契約をしてくれる保証もないからです。
そのため、不動産屋にとってはいかに「自分のお店で契約してもらうか」が大切です。
何かお客さんを囲い込むための策があるのでしょうか?
「自分のお店」と委任契約をしてもらう
例えば、不動産を売りたい人が不動産屋に物件を持ちこんだ際、多くの場合「専属委任契約」を結ばされるはずです。
これは、「自分の不動産屋以外には物件を売却依頼しないでください」という契約です。
実は欧米ではこういった囲い込みは、買い手・売り手の利益を損なうとして禁じられていることが多いです。
しかし、日本においては野放しにされている現実があります。
不動産の紹介業務って?
売買を仲介する際には、必ず「値段の上乗せ」が行われます。
例えば、スーパーで売られている野菜。
あの野菜は、農家の人が作ったものを仕入れてお店に陳列しているわけですよね。
仮に白菜を1個100円で仕入れたなら、1個120円で売る。
その20円がスーパーの収益となるのです。
不動産屋も同様で、費用を上乗せして販売し、利益を得ています。
賃貸物件に入居を決めた客から、1か月分の手数料を得るだけでなく、家主が頼んでもいないのに勝手に鍵を交換、火災保険・物損保険に加入させ、初期費用を上げます。
さらに家主から広告料名目で成功報酬を受け取る業者も少なくありません。
参考文献:価格と儲けのカラクリ(p127-128)
本来、不動産屋が広告料という名目で、家主から謝礼を受け取るのは、宅建業法では違法とされています。
しかし、実際にはこんな手口で稼ぐ危険な業者もいるので注意が必要でしょう。
不動産の管理って?
不動産屋を支える最も重要な稼ぎが、「不動産管理」という定期的な収入です。
管理の主な内容としては、
- 入居者との契約
- 金銭のやりとり
- 建物の清掃
- 設備の点検
などを貸主の代わりに行います。
つまり管理業務とは、「家主に代わって物件の設備・運営をフォローしていくこと」を指します。
管理業務は仲介とは違って、安定した仕事になります。
なぜなら家主さんから管理を依頼され、「賃料の数パーセントを毎月貰える契約」になっているからです。
そのため管理物件の多さが、不動産屋の生命線となるでしょう。
最後に
このように、町の不動産屋は「仲介や管理」で主な収益を得ています。
町でお客さんが入っていない不動産屋は、もしかしたら仲介料は少なくても、たくさんの物件を管理することで、安定した収入が確保しているのかもしれません
また収入は少ないけれど、社長が一人で運営していて、人件費が少ない。
あるいは地主のために毎月の店舗費用がいらないといった好条件が揃っているのかもしれませんね。
https://it-information-engineering.com/store-karakuri
https://it-information-engineering.com/why-not-crushed