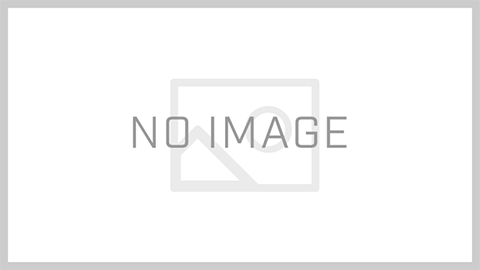- 文章力の重要性が増している理由
- KJ法の実践方法
文章を書く機会が増えています。
仕事上のやり取りは、電話ではなくメールで行う。
また様々な業界で、LINEやグループチャットを利用することが一般的になりつつあります。
そのため以前に比べると電話によるやり取りはもちろん、対面的なコミュニケーションを取る機会は減っています。
電話が発明された頃には、電話越しでのコミュニケーションが重要視されるようになりました。
今後はそれと同様に、文章力が重要視される時代がやってくるのでしょう。
文章が上手く書ける人は、将来的に多数のメリットを享受できるはずです。
この記事では、
- 文章力の重要性が増している理由
- KJ法の実践方法
をご紹介したいと思います。
「文章力」の重要性が増している理由
そもそも私たちは「なぜ、文章を書く」のでしょうか?
それは突き詰めると、「相手に”何か”を伝えたいから」というシンプルな答えに行き着くのだろうと思います。
これは言い換えると、
文章力がなければ、自分の思い通りに相手と意思疎通できない
ことを意味します。
例えばSNSを利用した、友人や恋人とのやりとりで考えてみます。
適切な文章が書けなければ、友人とのトラブルに発展したり、恋人との関係を継続できない可能性が高まります。
またビジネスで支離滅裂、誤字脱字のある文章を書けば、信用を失うことなるかもしれません。
インターネットが広がった現代においては、
文章力がある = 他者と円滑な関係を築く能力がある
と、言い換えられるでしょう。
ただこのように文章力が強力な武器となったのは、最近のことです。
なぜなら従来、文章力が重視されていたのは、作家やライター、記者といった、一部の職業に限られていたからです。
しかし今、それ以外の人にとっても、文章力の重要性が増している。
今まで文章を書く機会が少なかったのに、急に必要となれば、多くの人は戸惑います。
けれども、社会はこれからも変化し続けます。
近い将来、人口知能はあらゆる場所で利用され、モノのIoT化は加速していきます。
これからの時代、文章力を身につけることはあなたにとって大きな武器となるはずです。
文章力の磨き方(KJ法)
断片を繋げる文章術
文章を書く際の有名なテクニックの一つに、KJ法があります。
KJ法とは、
「バラバラに散らばっている情報から必要なものを取り出し、整理してまとめる手法のこと」
を言います。
考案者である、文化人類学者の川喜田二郎氏(東京大学名誉教授)のイニシャルを取って、”KJ法”と名付けられました。
文章力は言うなれば、アイデアに似ています。
単語と単語を組み合わせ、一つの文章として成り立たせる。
そのつなぎ目が少し違うだけで、文章のリズムや景観は一変してしまうのです。
そしてアイデアというのは、いつひらめくか分かりません。
時と場所を選ばず、突然頭の中に浮かんでくることも多いです。
ただ、『アイデアの作り方』の中で「ヤング」が指摘するように、アイデアが生まれるまでには、5つのステップを踏まなければなりません。
アイデアが湧いてこない場合、以下のステップを踏み忘れているのかもしれません。
- データ集め
- データの咀嚼
- データの組み合わせ
- 発見した!の瞬間
- アイデアのチェック
アイデアの想起を必要とする、「文章を書く」という作業において
- データを集める
- データを読み解く
- 組み合わせる
というプロセスは欠かせないものであり、有効な手段になります。
KJ法は、文章を書くための一つのテクニックです。
無数の情報を集め、整理し、組み合わせることで、アイデアが湧いてきます。
その湧いてくるアイデアが文章になります。
企業や学校でも取り入れられている
なぜこのような手法が、生まれたのか?
それは、文化人類学ではさまざまなフィールドワークが必要になるからです。
フィールドワークで得た、数々の発見と手に入れた膨大な情報をまとめることは、とても難しい。
その問題を解決するために、KJ法は生み出されました。
付箋に情報を散り散りにまとめて、後で統合する。
バラバラで規則性や関連性がよくわからない情報を、適当に書きだしてみる。
すると、それらには意外な関連性があることが分かってきます。
関連性のない事柄に関連性を見出し、繋ぎ合わせること。
情報を取捨選択し、まとめていく過程で、新たなアイデアは生まれてくるのです。
あまりにも有用な手法のため、企業や学校などの教育現場でも用いられています。
実際にKJ法をためしてみよう
1) テーマを決める
KJ法を行うために必要なモノ。
それは、思いついたことを書き出すための、ノートや付箋です。
パソコンの方が思いつきをまとめやすいという方は、それでも構いません。
まず初めにテーマを決めます。
ちなみに今回の記事は、KJ法を使って書いてみました。
「文章が苦手な人でも、上手く文章をまとめられる方法」
というテーマ設定をした上で、記載しています。
2) アイデアの書き出し
テーマが決まれば、次はアイデアの書き出しです。
思いつくことをひたすら紙に書いてみます。
それぞれの紙に発想ごとに区切って、書き出してみてください。
頭の中に思い浮かんだものだけでなく、調べた情報でも、テーマに関係しそうなものなら、何でもオーケーです。
3) 情報のグループ化
次に無造作に書きだされた情報を、グループ化する作業です。
内容が類似しているものをまとめていきます。
分類の方法には、特に決まりがありません。
「これとこれは関連してそうだ!」
とみなさんが思われたものを繋げてみてください。
主観的な視点で大丈夫です。
ただし注意が必要なのは、どこのグループにも属さないアイデアの存在です。
それらは使用しませんので、端っこにどけておいてください。
4) 名前をつける
グループ化が終われば、それぞれに名前をつけていきます。
例えば、
- 鉄棒
- ブランコ
- すべり台
という単語がグループにあるのであれば、「公園」という名前をつけます。
どんな名前をつけるかは発想しだいなので、センスが問われるかもしれません。
5) グループを関連付ける
まとめたグループごとに、名前をつけていきました。
すると、今までは別々のものだと思っていたグループに関連性が発見できるかもしれません。
もし、関連性が見られるようであれば、グループを隣同士にしておきます。
こうすれば全体像が見やすくなり、関連付けがしやすくなります。
6) 全体をまとめ、一つに繋げる
最後にグループとしてまとめた内容を吟味しながら、グループ間を繋げていきます。
その際に、
- 起承転結を帯びた文章をどうやって作ろう?
- 接続詞は何を用いたらいいか?
を見当します。
どの接続詞を使うかで、文章のリズムや読みやすさは一変します。
「私はKJ法の素晴らしさを実感しています。」
「私はKJ法が素晴らしいことを実感しています。」
この2文は同じ意味を持ちますが、読者への印象はまったく異なるのではないでしょうか?
接続詞は文章にとって、「接着剤」のようなもの。
繫ぎ目をしっかりと合わせないと、ほころびが出ます。
慎重に選ぶようにしましょう。
最後に
一度やってみるとわかりますが、KJ法を使うと、文章は格段に書きやすくなります。
なぜならこの方法だと、
- 思い付いた内容をとにかく書きだす
- あとでまとめて分類する
という流れなので、思い浮かんだ内容を忘れずに書き残すことができます。
また、
- 文章の順序を考えすぎて、何も書けない
- 書いては消してを繰り返し、文章が前に進まない
ような方は、より効果を実感しやすいと思います。
そのような方は、ぜひKJ法を試してみていただきと思います。