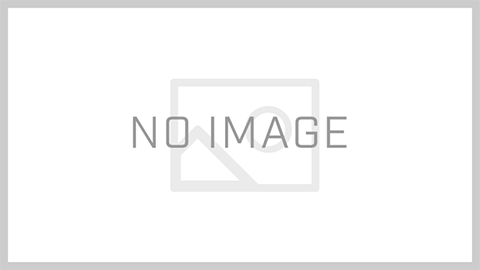村上龍エッセイの特徴は、切れ味鋭い抜群の批評眼にあります。
言いにくいことを一刀両断にバッサリと切り裂く口調は、清々しさに溢れています。
しかし本作『おしゃれと無縁に生きる』においては、「〜ではあるけれども、結局は分からない」という曖昧な表現が目立っていました。
(2024/04/19 03:29:20時点 Amazon調べ-詳細)
いい悪いの2択ではなく、「分からないものは、わからん」とハッキリと主張するのが、村上エッセイの特徴ではあるけれども、いつもよりその量が多く感じました。
これは言い換えると、社会に不確定要素が増えたことにより、未来を予測したり、現状を分析するのが難しくなったのかもしれません。
本作で語られる各トピックは、1〜3ページと短い枚数で記されています。
芸術、経済、労働、スポーツ、ワイン、ITといった、幅広い分野で構成されたエッセイ集です。
目次を一部紹介すると、以下のような感じ。
- おいしいワイン
- 日本が誇れるもの
- インターネットと読書
- オリンピックと貧困
- ITの皮肉
- アベノミクスの功罪
当記事では、以下の内容をご紹介していきます。
- 「仕事ができるタイプ」におしゃれな人間はいない
- 努力できることが才能
- 質問をするためには、知識必要
“村上龍”作品のスタイル
村上龍氏は、現在66歳(2018年時点)と高齢に差し掛かったものの、社会に対する関心は衰えないと言います。
その好奇心が書籍を書くための原動力になっているとのこと。
『希望の国のエクソダス』では、日本に希望を失った若者が、徒党を組んで国外へ逃亡していく社会を描き出しました。
また『共生虫』では、社会問題化する”引きこもり”を主人公にして、彼らの是非を訴えた。
過去作からも分かるように、社会と小説をリンクさせた上で、問題提起を読者に迫っていくスタイルです。
“仕事ができるタイプ”におしゃれな人間はいない
多くの男性誌では、ファッションや恋愛などの記事が記載されています。
- 出来る男の服装!
- 女性とのデートにはこの服!
おしゃれに服装を着こなせば、できる奴に見られるだろう。
そう思ってしまいますが、村上さんは、「仕事ができるタイプ」におしゃれな人間はいないと言います。
ところで、わたしの周囲の、著名な文化人とか、仕事ができるメディア関係者の中には、「おしゃれ」な男がいない。
その理由はまた簡単で、充実した仕事をしていて、当然のことながら忙しく、ファッションに気を使うような時間的余裕がないからだ。
みんな経済力に応じた「ごく普通の格好」をしている。
凝ったものは着ていない。
他人や女性から「おしゃれですね」などと言われたいと思う男はいない。
「できる男に見られたい」という想いは、あくまで願望に過ぎません。
願望は自分の手元にはないため、手に入れたいもの。
つまり「憧れているもの」を指します。
憧れの自分になるため、ファッションに気を遣う。
もちろん、そうした努力は必要だと思います。
武道の世界では、初めに”型”を徹底的に叩き込みますし、書道の世界では、ひたすら手本通りに書き写す訓練を行います。
初めに中身から入るのではなく、形を身につけるのは、どの分野であれ大切なコトであります。
ですので、まずとっかかりとして、服装に気を遣う(=形から入る)ことは否定しません。
ただ「本当のできる男になりたい」のなら、もっと別の努力をする必要があるでしょう。
あくまで、ファッションは「できる人のイメージ」を連想させるものであって、目的とはなりえません。
本当に重要なコトは、目的を達成するために、適切な道順を踏んでいくこと。
「出来る男になりたい」という欲望を達成するために、ファッションを意識した結果として、目標からは遠ざかる。
それでは本末転倒になってしまいます。
望むものを手に入れる手法を間違えば、いつまで立っても目的地へは辿り着けないのですから。
「仕事ができるタイプ」におしゃれな人間はいない
あくまでファッションは「できる人」のイメージを連想させるだけ
努力は才能である
アーティストやプロ選手になるためには、「才能か努力のどっちが必要?」という議論が盛んに行われています。
私自身、「何かで秀でている人は、努力よりも才能が大切なんだ」と思っていました。
しかし村上さんは、努力と才能を分けるのは間違っていると言います。
才能というのは、その人にぺたっと張り付いているわけでも、内蔵のように体内、脳内に存在しているわけでもない。
努力を続けることができる、それが才能で、それ以外にはない。
ではどのようなきっかけで、このような考えに至ったのでしょう?
それは、サッカーの元日本代表である中田英寿選手との出会いだったといいます。
練習場に着くと、中田が一人、ずぶ濡れになりながら、フリーキックの練習をしていた。
他には誰もいなかった。
こんな雨だし、すぐに終わるだろうと思いながら見ていたが、中田は、暗くなってボールが見えなくなるまで蹴り続けた。
なんで、あんな雨の中、たった一人でボールを蹴ってたの?
その夜、食事しながら、そう聞くと、質問の意味がわからないという表情で、中田は答えた。
「だって、雨でも、サッカーのゲームは中止にならないですよ」
中田英寿とつきあっているとき、いつも思った。
「どんな人間でも、これだけ練習したら、きっとそれなりの選手になれるだろう。これだけの練習ができるというのが才能なんだ」
私たちは努力と才能を、分けて考えてしまいます。
成功している人を見て、「あの人には才能があるからできるんだ」と羨ましがり、「自分には才能がないからダメだ」と卑下してしまう。
確かに、生まれ持った才能は違うでしょう。
誰だって得意なことがある一方で、「これだけは無理だ」といった苦手なことがある。
スポーツが得意な人もいれば、絵が得意な人もいる。
才能とは、個性とも言い換えられるのかもしれません。
素材が違えばでき上がる料理が変わるように、個性が違えば、成功できる分野も異なります。
どれだけ憧れたとしても、自分に適さない分野で勝つのはどうしたって難しいです。
ただある程度のレベルまでは、努力でカバーすることができるのです。
そして才能があったとしても、努力なしには才能の花は開きません。
努力できるか否かも、才能である。
中田選手のように、”努力ができる”という才能を持っているならば、特定の分野で抜きん出ることは可能なのです。
“質問する能力”を養うために
質問を考えるのは簡単ではありません。
なぜなら、私たちは幼いころから”質問するという訓練”を受けていないからです。
学校に入学すれば、“指導する者”と“指導される者”はハッキリと分かれています。
先生が生徒に向けて授業を行う。
その空間では、「先生から生徒へ」という図式は存在するけれども、「生徒から先生へ」という図式は存在しません。
教師と生徒による対話は、ほとんど行われることがなく、教師から生徒への一方通行のコミュニケーションが行われています。
大学のような専門課程に入ったところで、あまりこの傾向には変わりがありませんでした。
本書では、指示や命令が横行する環境では、質問する能力は養われないと指摘しています。
質問するためには、ある程度の知識が必要になる。
たとえば大きなトピックスになったSTAP細胞だが、専門家に質問するためには、幹細胞、発生と文化など、生物学に関するある程度の知識がなければいけない。
(省略)
薬学系のある大学で、もっとも人気がある教授がいて、その授業は、まず最初に、「はい、質問は?」と促されるのだそうだ。
学生たちに質問がないと、「じゃあここまで」と教授は途中で帰ってしまう。
学生たちは、前日までに教科書を読み込み、質問を考えて授業に臨むことになる。
一年間で、その教授が受け持つ学生たちの成績は格段にあがるらしい。
私は「質問をするためには、ある程度の知識が必要だ」といったことを、今まで考えたことがありませんでした。
質問できないのは、「元々の語彙力がない」だとか「相手の話に興味が持てていない」とか、能力や感じ方の問題なのだと考えていました。
けれども、ある程度の知識があれば質問できる。
これは言い換えると、質問は技術だということです。
今どれだけ質問する能力がない人であれ、自分の頑張り次第で鍛えられる能力。
質問力は、「何を知りたいのかを予め把握しておき、自分の思っていることを相手に正確に伝える」という技術なのです。
最後に
今回は、本作『おしゃれと無縁に生きる』の中で、興味が湧いたトピックを取り上げてみました。
一つの話題はたった数ページで完結しているにも関わらず、
- こんな考え方もあるんだな
- 自分が知らない世界があるんだ
価値観が揺さぶられ、好奇心が刺激される内容ばかりでした。
村上氏の過去作と比べると、パンチ力は少ないかもしれません。
けれども、今まで村上作品をあまり読んだコトがない人にとって、入門書として最適な1冊だと思います。
(2024/04/19 03:29:20時点 Amazon調べ-詳細)
(2024/04/19 03:30:44時点 Amazon調べ-詳細)
本作は、村上龍氏のデビュー作にして問題作である処女作です。
退廃的な毎日を過ごすアンダーグラウンドな若者たち。空虚感や孤独感といった誰もが抱く青春の苦悩を、鮮明に描きだした一冊です。
私自身は、大学時代に読みましたが途中で挫折してしまいました。
なぜならドラッグやセックスに溺れる若者たちが、ありありと目の前に感じる程のリアルさがあり、気分が悪くなってしまったからです。
けれども、エネルギーに満ち溢れた本作は、初めに読む村上作品としてオススメです。
「この国には何でもある。本当にいろいろなものがある。だが希望だけがない。」
ネットが発展する一方で、経済が停滞する日本。今この国では、バブルの頃のようなエネルギーはなく、死にゆく国への渦中にあるのかもしれません。
「良くしたい」と思った所で、あまりにも複雑に絡まりあった糸をほぐすのは簡単ではありません。
ただ私たちは傍観して見ているしかないのか。
これからの未来を生きる若者たちにこそ、読んで欲しい一冊です。